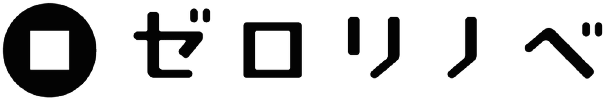2024.04.02 更新
奨学金の住宅ローン審査への影響とは?借りる際の注意点を4つ紹介

「奨学金の返済は住宅ローン審査に影響する?」
「奨学金の影響で住宅ローンの審査に通らないこともある?」
奨学金返済が住宅ローン審査へどのように影響するのか、気になる人も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、奨学金が住宅ローン審査へ与える影響は小さいです。
ただ、ローン審査書類への記入漏れがあったり、申告を隠してしまったりすると、「審査に通らない」「ローンの一括返済を求められてしまう」などの恐れがあります。
そのため、奨学金の種類や金額の大小に関わらず、住宅ローン審査において奨学金の返済は正直に申告しなければなりません。
本記事では、奨学金が具体的に住宅ローン審査へどのような影響を与えるのか具体的なケースと、審査に通りやすくなるポイントをご紹介します。
また、奨学金を返還中の場合はどのような住宅予算を立てればいいのか、目安をご紹介しているので参考にして下さい。
Advisor

Author

[著者]
ゼロリノベ編集部
元銀行員・宅地建物取引士・一級建築士が在籍して「住宅ローンサポート・不動産仲介・リノベーション設計・施工」をワンストップで手がけるゼロリノベ(株式会社groove agent)。著者の詳しいプロフィール
目次
奨学金の住宅ローン審査へ与える影響とは?影響は少ないと考えられる
結論、奨学金は住宅ローン審査に影響を与えることは少ないです。
なぜなら、住宅ローン審査は返済能力や返済負担率が重視されるからです。
そのため、奨学金を返済中だとしても安定した収入があり住宅ローンを毎月返済できると判断されれば、審査には問題なく通ります。
ただし、奨学金とはいえ借り入れであることには変わりありません。
住宅ローン以外の借り入れが現在もあるという点においては、審査はより厳格になるでしょう。
住宅ローン審査の際には、「奨学金を合計でいくら借りているのか」「毎月いくら返済しているか」の点がチェックされます。
奨学金が住宅ローン審査へ与える影響とは?2つのケースを紹介
 では、奨学金が住宅ローン審査へ影響する場合にはどのようなケースがあるでしょうか?
では、奨学金が住宅ローン審査へ影響する場合にはどのようなケースがあるでしょうか?
大きく2つのケースが考えられます。
- 住宅ローンの返済負担率へ影響する場合
- 奨学金の延滞や滞納が審査へ影響する場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1.住宅ローンの返済負担率へ影響する場合
奨学金は住宅ローンの返済負担率に影響を与えます。
住宅ローン審査における年間の返済負担率の目安は、およそ30〜35%とされています。
年収にも左右されますが、一般的にはこの数値を超えると審査に通りにくくなります。
奨学金込みで返済負担率が基準を超えてしまうとすれば、借入額を見直さなければなりません。
労働福祉中央協議会の「奨学金や教育負担に関するアンケート調査」によれば、奨学金の月々の返済額は平均すると15,226円となっています。
住宅ローンの返済と奨学金の返済を合計した返済負担率が30〜35%ほどに収まるように返済計画を立てていきましょう。
ただし、上記の30〜35%は、あくまで金融機関側が基準とする目安です。
実際に日々の生活の中でローンを無理なく返済していくには、返済負担率20%前後に収めておくのが理想になります。
関連:住宅ローン返済比率20%の理由と考え方【年収別の借入額の目安表】
2-2.奨学金の延滞や滞納が審査へ影響する場合
奨学金が住宅ローン審査へ影響するもう1つのケースは、延滞や滞納の履歴があった場合です。
日本学生支援機構は個人信用情報期間に加盟しているため、奨学金の延滞や滞納は個人信用情報へ履歴として残ります。
具体的には、奨学金の返済が始まって6ヵ月が経過した時点から毎月の返済がチェックされ、3ヵ月以上の滞納があった場合に履歴として残ります。
延滞や滞納があった人でも、3ヵ月未満であれば個人信用情報へは登録されず住宅ローン審査への影響はありません。
また、3ヵ月以上の延滞や滞納があった場合でも、返還完了の5年後に履歴は削除されます。
奨学金には返還が困難な状況の場合に申し出ることで猶予してもらえる「返還期限猶予」もあります。
他の借り入れとは違い、延滞や滞納が即座に履歴として残る可能性は比較的低いものであるといえるでしょう。
住宅ローン審査時に奨学金の返済を申告すべき2つの理由とは?
 冒頭で述べたとおり、奨学金は住宅ローン審査時に申告すべき内容です。
冒頭で述べたとおり、奨学金は住宅ローン審査時に申告すべき内容です。
その理由として以下2つのポイントに絞って解説していきます。
- 奨学金の返済を申告しなくてもバレるから
- 嘘や申告漏れは住宅ローン審査に影響するから
お金にまつわる約束ごとは信頼関係が重要であり、嘘や隠しごとは悪い結果へとつながります。
奨学金と住宅ローン審査においても同じであるため、本章でしっかり理解していきましょう。
3-1.奨学金の返済を申告しなくてもバレるから
日本学生支援機構は個人信用情報機関に加盟しているため、個人の情報は全国銀行協会を通して各金融機関へ共有されます。
具体的には以下の項目が個人信用情報として共有されます。
本人の個人情報として氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先等、契約の情報として、貸与額・最終返還期日等が登録されます。
その他に延滞・代位弁済・完済等の返還状況も登録されます。
また、奨学金支払口座(リレー口座)で支払状況を確認する方法もあります。
さまざまな支払いの中で奨学金の返還額が小さいため、仮に住宅ローン審査の際に申告しなかったとしましょう。
しかし、奨学金をはじめとする借り入れ状況はすべて金融機関に把握されています。
奨学金の返還が後々ばれた場合、金融機関によっては一括返済を求められてしまう恐れもあるため、事前に申告しておきましょう。
3-2.嘘や申告漏れは住宅ローン審査に影響するから
住宅ローン審査は信頼関係が重要であり、嘘があると金融機関へ与える印象も悪くなり、審査に通らなくなる恐れがあります。
「奨学金は借金」という意識が薄いがゆえ、うっかり申告を忘れてしまうこともあるでしょう。
申告漏れの場合も、毎月の変換状況を把握していない、お金の管理が甘い印象につながり、審査に影響する可能性もあります。
審査中であれば審査が打ち切られたり、金利が高くなってしまったりと不利な状況につながります。
住宅ローン審査においては、嘘や申告漏れをなくして包み隠さず開示することが大切です。
奨学金返済中でも住宅ローンを借りられる?審査に通りやすくなる4つのポイント
ここからは、奨学金返済中でも住宅ローン審査に通りやすくなるポイントを4つにまとめて紹介します。
- 住宅ローンの返済負担率を抑える
- 返済履歴を積み上げる
- 延滞や滞納の履歴が消えるまで待つ
- 配偶者に住宅ローン審査をお願いする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1.住宅ローンの返済負担率を抑える
住宅ローン審査における返済負担率は手取り年収の30〜35%ほどです。
奨学金返済中でも、返済負担率を30〜35%よりさらに低く抑えられれば、審査にも通りやすくなる可能性があります。
返済負担率を抑えるには以下の方法が考えられます。
- 頭金を入れて借入額を下げる
- 奨学金の「減額返済制度」を利用する
- ペアローンを組む
- 金利の低い住宅ローンを申し込む
上記のような方法により、返済負担率が30%を下回るように抑えられれば、住宅ローン審査もとおりやすくなる可能性が高いです。
ただし、奨学金の「減額返済制度」やペアローンなどは一定の条件を満たす必要があるため、自身に最適な方法を選択していきましょう。
4-2.返済履歴を積み上げる
住宅ローン審査の基準は金融機関ごとに異なるため、返済履歴を積み上げて信用力を高めると審査に通りやすくなるケースもあります。
過去に延滞や滞納の履歴があっても、現在の収入と奨学金返済が安定していれば返済能力が高いと判断されるからです。
奨学金を滞りなく返済している履歴が重要になるため、滞納や延滞があった際は即座に返還していきましょう。
また、奨学金の「減額返済制度」は返還額を下げられるため、延滞や滞納を防ぐ方法としても活用していくことをおすすめします。
4-3.延滞や滞納の履歴が消えるまで待つ
大幅な延滞や滞納がある場合、履歴が消えるまで待ちましょう。
奨学金の延滞や滞納履歴は、完済後5年経過すると削除されます。
履歴が削除されれば、過去の延滞や滞納は住宅ローン審査に影響しません。
余剰資金がある場合は、住宅ローンの頭金に充てずに奨学金を繰上げ返済する方法もあります。
奨学金を早めに完済しておくことで、延滞や滞納の履歴を早い段階で消せるでしょう。
4-4.配偶者に住宅ローン審査をお願いする
奨学金の返済が気がかりな人は、配偶者に住宅ローン審査をお願いする方法も検討しましょう。
収入や勤続年数などが配偶者と同等の場合、同じ条件で住宅ローン審査を受けられます。
同じ条件であれば、信用情報のきれいな人が契約する方が審査は通りやすくなるでしょう。
また、配偶者を契約者とした収入合算のローンであれば、借入額も増やせる可能性があります。
お申込人の収入に、一定の収入のある親族の方(収入合算者)の収入を合算して、その合算した金額をもとに住宅ローンを借り入れることをいいます。お申込人が単独で借りるよりも多い金額の融資を受けられる可能性があります。
引用:ペアローン・収入合算
ただし、住宅ローン控除を受けられるのは契約者のみである点や2人ともが団体信用生命保険に加入できないなどデメリットもあります。
奨学金と住宅ローン審査に関するよくある質問
最後に、奨学金と住宅ローン審査に関するよくある質問を紹介します。
- 住宅ローン審査の際に奨学金の申告は不要?
- 住宅ローン審査の際の奨学金の申告漏れはどうなる?
- 妻が奨学金を返済していると住宅ローンの審査に影響する
住宅ローン審査に疑問がある方は、最後までご覧ください。
5-1.住宅ローン審査の際に奨学金の申告は不要?
住宅ローン審査の際に奨学金の申告は必要です。
住宅ローンを申し込む際、収入や支払い状況を正しく報告しなければならないからです。
仮に、申告をしなくても、個人信用情報を辿れば奨学金を返済中であることが金融機関にばれます。
住宅ローンを申し込む際に申告していなかったことが発覚すると悪い印象を与えるため、審査に影響してしまう可能性があります。
5-2.住宅ローン審査の際の奨学金の申告漏れはどうなる?
奨学金の申告漏れは以下のようなトラブルの原因となりえます。
- 審査を打ち切られる
- 金利が高くなる
- 一括返済を求められる
住宅ローンの契約には信頼関係が大事です。
うっかり申告を忘れていた場合、お金の管理が甘い人という印象を与えてしまい、不利な状況になります。
また、金融機関によっては一括返済を求められるケースもあるため、注意が必要です。
5-3.妻が奨学金を返済していると住宅ローンの審査に影響する?
ペアローンや収入合算でローンを申し込む場合、妻の奨学金返済も住宅ローン審査でチェックされます。
延滞や滞納が何度も続いていたり、信用情報に履歴が残っていたりすると、ペアローンや収入合算で審査がとおりづらくなる場合もあるでしょう。
単独ローンの場合は配偶者の奨学金返済は審査に影響しないため、混同しないよう注意しましょう。
5-4.実際に奨学金を借りている状態で住宅ローンを組むとどうなる?
具体的に、奨学金の有無によってどれくらい借入額が変わる可能性があるのか、シミュレーションしてみましょう。
- 年収:500万円
- 月の返済額:10万円
- 返済期間:35年
- 金利:1.3%
上記の条件で試算した場合、借り入れ可能額は約3,372万円となり返済負担率は24%です。
続いて、奨学金を毎月16,000円変換している場合を考えてみましょう。
- 年収:500万円
- 月の返済額:8.4万円(+1.6万円=10万円)
- 返済期間:35年
- 金利:1.3%
この場合、借り入れ可能額は約2,833万円となり返済負担率は20.1%です。
実際に借りられる金額が約500万円ほど少なくなりました。
金利や返済額の調整もあるため、必ずしもこのような金額になるとは限りませんが、奨学金を考慮した住宅ローンは借入額へ影響する点を理解しておきましょう。
まとめ
奨学金は金利や返済額も比較的小さいため、滞りなく返還し続けていれば住宅ローン審査へ大きく影響しません。
ただし、故意的に申告しなかったり、申告を忘れたりしてしまうと、審査で不利になってしまう恐れがあります。
住宅ローン審査の際には正確に申し出て、奨学金の返還を考慮した住宅ローンを組むようにしましょう。
また、審査が不安な人は「4.奨学金返済中でも住宅ローンを借りられる?審査に通りやすくなる4つのポイント」も参考にしてください。
ゼロリノベでは小さいリスクで家を買う方法に関するオンラインセミナーを毎週開催しています。ぜひ検討してみてください。