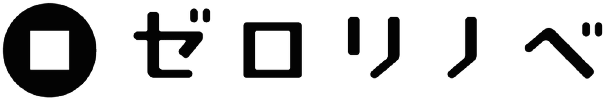2024.04.02 更新
住宅ローン控除を受けられる築年数とは?古い中古住宅でも控除を受ける方法|2022年改正

「築年数が古い物件は住宅ローン控除を受けられない?」
「昭和57年以前に建築された物件が控除を受ける方法はない?」
中古住宅を購入すると、住宅ローン控除が受けられるか気になりますよね。
住宅ローン控除の対象は昭和57年以降に建築された物件です。
しかし、昭和57年以前に建てられた物件でも、以下の方法によって住宅ローン控除を受けられます。
・耐震基準適合証明書を取得する
・既存住宅性能評価書を取得する
・既存住宅売買瑕疵保険に加入する
いずれも注意点や申請の流れなどを押さえておかなければ、住宅ローン控除を受けられなくなってしまうので、注意が必要です。
この記事では、築年数が古い物件でも住宅ローン控除を受けられる方法をくわしく掘り下げていきます。
具体的な手順や注意点、新築住宅の住宅ローンとの違いなども紹介しますので、ぜひ参考にして下さい。
※本記事に掲載している住宅ローン減税制度の概要・要件等は、2024年度の税制改正大綱の内容に基づいています
Advisor

Author

[著者]
ゼロリノベ編集部
元銀行員・宅地建物取引士・一級建築士が在籍して「住宅ローンサポート・不動産仲介・リノベーション設計・施工」をワンストップで手がけるゼロリノベ(株式会社groove agent)。著者の詳しいプロフィール
目次
住宅ローン控除とは?中古住宅は最大13年間の控除が受けられる
住宅ローン控除とは、住宅ローン残高に対する一定割合の金額が所得税から控除される減税制度のことです。
正式名称は「住宅借入金特別控除」と呼び、住宅購入者の負担を減らし、住宅購入が容易になるように考えられました。
ここからは、住宅ローン控除に関する以下のポイントに絞って解説していきます。
- 住宅ローン控除額|中古住宅でも最大35万円の控除
- 住宅ローン控除を受けるための条件とは?3つのパターンで解説
詳しくみていきましょう。
1-1.住宅ローン控除額|中古住宅でも最大35万円の控除
住宅ローン控除の控除率は0.7%であり、年末時点で残っている住宅ローン借入額をかけた金額が所得税から控除されます。
ただし、控除される住宅ローン借入額には上限が設けられており、最大で受けられる控除額にも上限があります。
| 新築住宅 | 中古住宅 | リフォーム | |
| 控除率 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 上限額 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 |
| 控除額(最大) | 35万円 | 21万円 | 14万円 |
| 控除を受けられる期間 | 13年 | 10年 | 10年 |
例えば、6,000万円の住宅ローンを借り入れた場合、受けられる控除額は5,000万円×0.7%の35万円が限度になります。
なお、住宅を購入した年度や住宅の区分によって、控除される住宅ローン借入額が変わるため詳しくは以下を参考にして下さい。
新築住宅:No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
中古住宅:No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
リフォーム:No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
1-2.住宅ローン控除を受けるための条件とは?3つのパターンで解説
また、住宅ローン控除を受けるための条件は各住宅ごとに異なります。
ここでは、以下の3パターンに分けて住宅ローン控除を受ける条件を解説していきます。
- 新築住宅に適用される条件
- 中古住宅に適用される条件
- リフォームや増改築に適用される条件
条件の違いを押さえておかなければ住宅ローン控除の適用外となってしまうため、注意して下さい。
1-2-1.新築住宅に適用される条件
新築住宅の適用条件は以下の通りです。
・住宅取得後から6ヵ月以内に入居し、居住していること
・住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上を居住用としていること
・控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済するものであること
・贈与による住宅取得ではないこと
・その他の課税の特例の適用を受けていないこと
参照:No.1212一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
令和5年12月31日までに建築確認を受けた家屋の場合、床面積が40㎡以上50㎡未満でも控除の対象となります。
ただし、所得の条件が2,000万円以下から1,000万円以下に変更となります。
また、2024年の改正により、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅は省エネ基準適合が必須となりました。
詳しくは「令和4年度税制改正のポイント」も参考にしてみて下さい。
1-2-2.中古住宅に適用される条件
中古住宅は「買取再販」と「買取再販以外」の2つに分けられます。
「買取再販」とは不動産業者が買取り、特定の増改築を行った住宅を購入するケースのことです。
不動産業者が買い取った日から2年以内かつ、建物が建てられてから10年以上経過している場合を指します。
買取再販の適用条件は以下のとおりです。
・住宅取得後から6ヵ月以内に入居し、居住していること
・住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上を居住用としていること
・控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済するものであること
・贈与による住宅取得ではないこと
・その他の課税の特例の適用を受けていないこと
・住宅が新築された日から起算して10年を経過していること
・特定増改築等に要した費用が、売買価額の20%以上に相当する金額であること
・特定増改築等に係る工事(※1)が行われていること
・以下のいずれかを満たしていること
(1)昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
(2)耐震住宅であると証明されていること参照:No.1211-2買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
※1:<特定増改築等の工事内容>
新築住宅の条件に加え、住宅が新築されてから10年を経過していることや、増改築費用が売買価格の20%以上に相当する金額であることなどが盛り込まれています。
なお、買取再販の場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅は控除の対象となりません。
「買取再販以外」は「買取再販」に当てはまらないケースを指します。
「買取再販以外」の適用条件は以下のとおりです。
・住宅取得後から6ヵ月以内に入居し、居住していること
・住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上を居住用としていること
・控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済するものであること
・贈与による住宅取得ではないこと
・その他の課税の特例の適用を受けていないこと
・以下のいずれかを満たしていること
(1)昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
(2)耐震住宅であると証明されていること
参照:No.1211-3中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
中古住宅の場合は「買取再販」と「買取再販以外」いずれも、昭和57年1月1日以降に建築されたものであること、もしくは耐震住宅であると証明されていることがポイントです。
詳しくは「住宅ローン控除の対象となる中古住宅の築年数とは|2022年改正」で解説していきます。
1-2-3.リフォームや増改築に適用される条件
新築住宅の適用条件は以下の通りです。
・住宅取得後から6ヵ月以内に入居し、居住していること
・以下のいずれかに該当すること
(1)床面積50㎡以上、床面積の2分の1以上を居住用としており、控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
(2)床面積40㎡以上50㎡未満、床面積の2分の1以上を居住用としており、控除を受ける年の合計所得が1,000万円以下であること
・リフォーム後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上を居住用としていること
・住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済するものであること
・その他の課税の特例の適用を受けていないこと
・リフォーム費用が100万円以上であり、その2分の1以上の額が自身の居住用部分の工事費用であること
参照:No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
100万円を超えるリフォームをローンを組んでおこなう場合には、控除が受けられます。
住宅ローン控除の対象となる中古住宅の築年数とは|2022年改正

ここまでは、住宅ローン控除の概要を紹介しました。
住宅ローン控除を受けるには、さまざまな条件がありますが、その中に建物の築年数に関する事項があります。
築年数に関する事項は、以下のとおりです。
▼昭和57(1982)年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)
※上記に該当しない場合は以下のいずれかであること
- 「耐震基準適合証明書」を取得している
- 「既存住宅性能評価書」による耐震等級評価が等級1~3である
- 「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している
ここからは、中古住宅が住宅ローン控除を受ける方法を、以下の3つのポイントに沿って解説していきます。
- 昭和57(1982)年以降に建築された物件は住宅ローン控除の対象
- 「現行の耐震基準」を満たす物件は築何年でも住宅ローン控除の対象になる
- 「耐火建築物」の場合も「昭和57(1982)年以降に建築」に統一
それぞれ詳しくみていきましょう。
2-1.昭和57(1982)年以降に建築された物件は住宅ローン控除の対象
中古住宅が住宅ローン控除を受けられるか否かを考えるポイントに、昭和57(1982)年以降に建築されたかどうかという点があります。
住宅ローン控除の要件は、2022年の改正によって以下のように緩和されました。
| 改正前 | 改正後 | |
| 要件 | 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること | 昭和57年(1982年)1月1日以降に建てられた住宅(新耐震基準)であること |
耐震基準とは、建築基準法によって定められた地震に対する耐久性を表す基準であり、過去3回に渡って見直しが行われてきました。
| 制定年 | 基準 | |
| 旧耐震基準 | 1950年~ | 震度5強程度の中規模地震でも建物が大きな被害を受けないこと |
| 新耐震基準 | 1981年~ | 震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないこと |
| 現行の耐震基準 | 2000年~ | 新耐震基準+地盤調査の義務化 |
2022年の改正によって、上記の新耐震基準を満たす建物は住宅ローン控除の要件に該当するようになりました。
そのため、昭和57(1982)年1月1日以降に建築された建物は控除の対象となります。
中古住宅で住宅ローン控除を受ける際のその他の適用条件は「1-2-2.中古住宅に適用される条件」を参考にして下さい。
2-2.「現行の耐震基準」を満たす物件は築何年でも住宅ローン控除の対象になる
では、昭和57(1982)年以前の建物はどうなるでしょうか。
結論からいえば、「現行の耐震基準」を満たしていれば住宅ローンの対象となります。
現行の耐震基準とは、先ほどの表のうち、2000年以降に建てられたものが該当します。
「現行の耐震基準」は、以下のいずれかを満たすことで申請が可能になります。
- 「耐震基準適合証明書」を取得している
- 「既存住宅性能評価書」による耐震等級評価が等級1~3である
- 「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している
昭和57(1982)年以前の建物も、上記の方法によって「現行の耐震基準」を満たすことで、住宅ローン控除の対象となります。
なお、昭和57(1982)年以前の建物は「1-2-2.中古住宅に適用される条件」が要件となるため注意が必要です。
2-3.「耐火建築物」の場合も「昭和57(1982)年以降に建築」に統一
2022年の改正前の要件は「家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること」とされていました。
「耐火建築物」とは、建物の主な材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含まない)、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物をさします。
そのため、2022年の改正前は住宅が「耐火建築物」に該当するか調べる必要がありました。
しかし、2022年の改正によって要件が「昭和57年(1982年)1月1日以降に建てられた住宅(新耐震基準)であること」へ統一されたため、現在は「耐火建築物」に該当するか調べる必要はありません。
昭和57年(1982年)1月1日以降に建てられているかを確認し、昭和57年(1982年)1月1日以前の場合は、先ほど紹介した以下の方法によって現行の耐震基準を満たすことで控除の対象となります。
昭和57年以前の中古住宅が住宅ローン控除を受ける方法
ここからは、中古住宅が現行の耐震基準を満たす方法を解説していきます。
現行の耐震基準は以下のように定められています。
震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないこと+地盤調査の義務化
上記を満たす方法は、前述した以下3つの要件のいずれかを満たすことです。
- 「耐震基準適合証明書」を取得している
- 「既存住宅性能評価書」による耐震等級評価が等級1~3である
- 「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している
この3つの概要を表にまとめましたので、以下を参考にして下さい。
| 耐震基準適合証明書 | 既存住宅性能評価書 | 既存住宅売買瑕疵保険 | |
| 申請者 | ・建物の引渡し前に申請する場合:建物の売り主 ・建物の引渡し前に仮申請する場合:建物の買い主 |
・基本は買い主 ・売り主(不動産業者、ハウスメーカー含む)が申請することも可能 |
・売り主が不動産会社の場合:売り主=不動産会社 ・売り主が個人の場合:検査事業者 |
| 申請先 | ・建築士(建築事務所) ・指定確認検査機関 ・登録住宅性能評価機関 ・住宅瑕疵担保責任保険法人 |
国土交通大臣が登録した第三者機関「登録住宅性能評価機関」 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
| 費用 | ・証明書の取得費用:3万~5万円程度 ・耐震診断の費用:10万~15万円程度 |
数万~数十万円 | ・保険料:住宅の床面積や保険金額によって異なる ・検査料:3~7万円程度 ・「保険付保証明書」の発行:無料 |
| 期間 | 早くても1ヵ月以上 | 1ヵ月程度 | 保険に加入できれば、住宅ローン控除に必要な「保険付保証明書」の発行は1週間程度 |
| 注意点 | ・補強工事が必要となるケースが多い ・建物の引渡し前に売り主が耐震基準適合証明書の発行を受けなければいけない |
・費用が数十万円と高額になる場合がある | ・旧耐震基準の住宅の場合、耐震基準適合証明書を取得しなければならない →その時点で住宅ローン控除の対象になる ・住宅引渡し前に保険契約しなければならない ・売り主が協力してくれなければ保険加入できない ・費用は買い主が負担する場合が多いが、売り主が負担したり、買い主と売り主で折半する場合もある |
では、それぞれどのようにすれば要件を満たせるのかを、次章からくわしく解説していきましょう。
3-1.耐震基準適合証明書を取得する
1つ目は「耐震基準適合証明書」を取得する方法です。
耐震基準適合証明書とは、建物の耐震性が建築基準法の定める現行耐震基準を満たしていることを証明する書類のことです。
建物の持ち主が「証明書を取得したい」と希望した場合に、建築士や指定性能評価機関などに建物の耐震診断を依頼し、実際の診断を経て発行されます。
「耐震基準適合証明書」に関しては以下のポイントに沿って解説していきます。
- 耐震基準適合証明書の取得方法
- 耐震基準適合証明書を取得する流れ
- 耐震基準適合証明書を取得する際の注意点
1つずつ見ていきましょう。
3-1-1.耐震基準適合証明書の取得方法
証明書の詳細や取得の方法を、以下の表にまとめました。
| 証明書を申請できる人 | ・建物の引渡し前に申請する場合:建物の売り主 ・建物の引渡し前に仮申請する場合:建物の買い主 →中古物件の耐震基準適合証明書は、原則として建物の引渡し前に売り主が発行を受けなければいけません。 それが難しい場合は、引渡し前に買い主が仮申請をする方法もあります。 ※詳細は後述 |
| 申請できる建物の条件 | ・登記事項証明書の床面積が50㎡以上である ・居宅として登記されている家屋である |
| 証明書を発行できる者=申請先 | ・建築士(建築事務所) ・指定確認検査機関 ・登録住宅性能評価機関 ・住宅瑕疵担保責任保険法人 |
| 申請時期 | 建物の引渡しより前 |
| 必要書類 | ・台帳記載事項証明書、または検査済証の写し ・検査登記事項証明書の写し、または建物登記事項証明書の写し ・物件状況等報告書 ・販売図面(間取り図) |
| 取得費用 | ・証明書の取得費用:3万~5万円程度 ・耐震診断の費用:10万~15万円程度 ※証明書の申請先機関によって異なります。 |
| 申請から取得までの期間 | 早くても1ヵ月以上 →実際に建物を調査するため時間がかかります。 |
| 証明書で受けられる控除 | ・住宅ローン控除 ・登録免許税の軽減 ・不動産取得税の軽減 ・固定資産税の減税 ・住宅取得等資金贈与の特例 ・マイホーム取得資金の相続時精算課税の特例 |
3-1-2.耐震基準適合証明書を取得する流れ
耐震基準適合証明書を取得し、住宅ローン控除を受けるには、以下の流れで手続きを行います。
<通常の流れ>
1)住宅の売買契約
2)耐震診断
3)耐震補強工事
4)耐震基準適合証明書の申請→発行
5)住宅の引渡し
6)住宅ローン控除の手続き(確定申告)
ただ、売り主が証明書の取得に協力してくれないなどの事情で事前の取得が難しい場合は、引渡し前に買い主が仮申請をおこなうこともできます。
仮申請で進める場合は以下のような流れで行いましょう。
<買い主が仮申請する流れ>
1)住宅の売買契約
2)耐震診断
3)耐震基準適合証明書の仮申請
4)住宅の引渡し
5)耐震補強工事
6)耐震基準適合証明書の発行
7)住宅ローン控除の手続き(確定申告)
3-1-3.耐震基準適合証明書を取得する際の注意点
耐震基準適合証明書を取得するには、いくつか注意点があります。
建物の中には、建築士や指定性能評価機関による耐震診断の結果、現行の耐震基準には適合しないと判断される住宅が多くあります。
適合しないと診断される住宅の場合、現行耐震基準を満たすように補強工事・改修工事を行わなければなりません。
住宅によっては、工事費用が住宅ローン控除の限度額である210万円を上回ってしまう可能性があります。
また、工事のために入居が大幅に遅れ、住宅購入の計画が狂ってしまう可能性もあります。
その場合は、耐震基準適合証明書による住宅ローン控除ではなく、次章から紹介する別の方法も検討してみて下さい。
また、耐震基準適合証明書によって住宅ローン控除を受けるためには、建物の引渡し前に売り主が証明書の発行を受ける必要があります。
中古住宅の購入後に買い主が申請して証明書を取得しても、住宅ローン控除は受けられません。
耐震基準適合証明書を取得する際は、「3-1-2.耐震基準適合証明書を取得する流れ」を参考に、手順に注意して下さい。
3-2.既存住宅性能評価書を取得する
2つ目は「既存住宅性能評価書」を取得する方法です。
「既存住宅性能評価書」は、中古住宅の性能を法律に基づいた10分野のチェックポイントに沿って点検・評価し、その結果を記載した書面です。
住宅の買い主や売り主などが、国土交通大臣の登録を受けた第三者機関「登録住宅性能評価機関」に「建設住宅性能評価(既存住宅)」の評価を依頼して取得するもので、評価結果は等級1から等級5までの5段階で表示されます。
この評価結果のうち耐震等級の評価が等級1〜3であれば、住宅ローン控除の対象になります。
3-2-1.既存住宅性能評価書の取得方法
既存住宅性能評価書の詳細や取得の方法は、以下の表にまとめました。
| 証明書を申請できる人 | 買い主が申請するケースが多いが、売り主(不動産業者、ハウスメーカー含む)が申請も可能 |
| 申請できる建物の条件 | 工事完了から1年以上の住宅 ※1年未満の場合でも、人が居住したものは申請可能です。 |
| 証明書を発行できる者=申請先 | 国土交通大臣が登録した第三者機関「登録住宅性能評価機関」 →一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページで検索できます。 |
| 申請時期 | いつでも |
| 必要書類 | ・建設住宅性能評価申請書(既存住宅)第八号様式 ・建設住宅性能評価申請書(既存住宅)別紙 ・委任状 ・同意書 ・申告書(住宅に関する基本的な事項を確認するための書類) ・設計図書など(案内図、平面図など) ・見取り図 ・新築時に建設住宅性能評価を受けた場合はその評価書、またはその写しおよび添付図書 など |
| 取得費用 | 数万~数十万円 ※評価機関と評価項目によって異なります。 |
| 申請から取得までの期間 | 1ヵ月程度 →実際に建物を調査するため時間がかかります。 |
| 証明書で受けられる控除 | ・住宅ローン控除 ・すまい給付金 ・贈与税の非課税枠拡大 ・地震保険料の割引き |
3-2-2.既存住宅性能評価書を取得する流れ
既存住宅性能評価書は、以下のような流れで取得します。ぜひ取得手続きの参考にして下さい。
1)登録住宅性能評価機関に「建設住宅性能評価(既存住宅)」を申請
2)建設住宅性能評価(既存住宅)の検査
3)既存住宅性能評価書の交付
3-2-3.既存住宅性能評価書を取得する際の注意点
既存住宅性能評価の申請には、数万〜数十万円の費用がかかります。
取得にかかる金額は、検査の内容によっても異なりますし、依頼する登録住宅性能評価機関によっても差があります。
場合によっては高額な費用が発生するので、評価機関に事前確認する必要があります。
3-3.既存住宅売買瑕疵保険に加入する
3つ目は「既存住宅売買瑕疵保険」に加入する方法です。
既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」があれば、住宅ローン控除を受けられます。
「既存住宅売買瑕疵保険」は中古住宅を売買した際に、不具合が見つかればその補修費用を補償してくれます。
加入するには建物の検査が必要です。
耐震基準に関する検査もあるので、この保険に加入できるということは現行の耐震基準を満たしているとみなされることにつながり、住宅ローン控除の対象となります。
3-3-1.既存住宅売買瑕疵保険の加入方法
既存住宅売買瑕疵保険の詳細と加入の方法、付保証明書の取得の方法も以下の表にまとめました。
| 加入申請できる人=被保険者 | ・売り主が不動産会社の場合:売り主=不動産会社 ・売り主が個人の場合:検査事業者 |
| 加入できる建物の条件 | 中古住宅で、 ・検査事業者による建物の現場検査 ・保険会社による書類審査 に合格したもの |
| 加入時期 | 証明書の取得、保険契約ともに住宅の引渡し前 |
| 保険の費用=保険料+検査料 | ・保険料:住宅の床面積や保険金額によって異なる ・検査料:3~7万円程度 ※この費用は、買い主が負担する場合が多いですが、売り主が負担したり、買い主と売り主で折半する場合もあります。 |
| 保険契約の必要書類 | ・保険証券発行申請書 ・契約内容の重要項目確認シート ・売買契約書の写し ・保証書の写し など |
| 証明書を発行する人 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
| 証明書の取得費用 | 無料 |
| 証明書取得までの期間 | 1週間程度 |
| 証明書で受けられる控除 | ・住宅ローン控除 ・すまい給付金 |
3-3-2.既存住宅売買瑕疵保険に加入する流れ
既存住宅売買瑕疵保険に加入して住宅ローン控除を受けるには、以下の流れで手続きを進めましょう。
1)検査事業者に検査と既存住宅売買瑕疵保険への加入を依頼
2)検査事業者が保険会社に保険申し込み
3)検査事業者による住宅の現場検査
4)保険会社による書類審査
5)「指摘事項」(=保険に加入するために必要な修理箇所)があれば、改修工事
6)検査と書類審査に合格すれば、保険会社が検査事業者に保険証券を発行
7)検査事業者が買い主に付保証明書を交付
8)住宅ローン控除の手続き(確定申告)
3-3-3.既存住宅で売買瑕疵保険に加入する際の注意点
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書を用いて住宅ローン控除を受ける場合、住宅の引渡しより前に保険契約を済ませる必要があります。
保険契約までのスケジュールは、「3-3-2.既存住宅売買瑕疵保険に加入する流れ」に記載してありますので、事前確認したうえで余裕を持ったスケジュールを組んでおきましょう。
旧耐震基準の住宅が既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、「耐震基準適合証明書」を取得する必要があります。
そのため、「耐震基準適合証明書」を取得した時点で住宅ローン控除の対象となり、瑕疵保険の加入が必須とはなりません。
前述したように、既存住宅売買瑕疵保険に加入するには、建物の引渡しより前に検査事業者による検査を受けなければなりません。
つまり、建物が売り主の持ち物である状態で検査が入るため、売り主の同意が必要になります。
売り主の協力がなければ、保険に加入することができないため、事前に売り主の同意を得ておく必要があります。
住宅ローン控除の築年数に関するよくある質問

最後に、住宅ローン控除の築年数に関するよくある質問を以下の順序でご紹介していきます。
- 住宅ローン控除の築年数に関する国税庁の記載は?
- 住宅ローン控除の築年数に関する要件撤廃はいつから?
- 住宅ローン控除は昭和57年以前の物件でも受けられる?
- 住宅ローン控除は築20年以上の物件でもう受けられる?
1つずつ紹介していきます。
4-1.住宅ローン控除の築年数に関する国税庁の記載は?
住宅ローン控除と中古住宅の築年数に関する国税庁の記載は以下の通りです。
1) 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
2) (1)以外の場合は、次のいずれかに該当すること。
引用:No.1211-2買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
なお、中古住宅の住宅ローン適用条件は「1-2-2.中古住宅に適用される条件」にて解説しているため、参考にして下さい。
4-2.住宅ローン控除の築年数に関する要件撤廃はいつから?
住宅ローン控除の築年数に関する要件撤廃は2022年からです。
なお、改正の内容は以下のとおりです。
・入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。
・控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。(チラシはこちら)
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
引用:令和4年度税制改正のポイント
住宅ローン控除の築年数に関する内容は、間違えやすい箇所でもあるので、注意しましょう。
4-3.住宅ローン控除は昭和57年以前の物件でも受けられる?
住宅ローン控除は昭和57年以前の物件でも受けられます。
昭和57年以前の物件が住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 「耐震基準適合証明書」を取得している
- 「既存住宅性能評価書」による耐震等級評価が等級1~3である
- 「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している
上記の要件を満たす方法は「昭和和57年以前の中古住宅が住宅ローン控除を受ける方法」にて解説していますので、ぜひ参考にして下さい。
4-4.住宅ローン控除は築20年以上の物件でもう受けられる?
住宅ローン控除は築20年以上の物件でも受けられます。
築年数ごとに以下の表にまとめましたので、ぜひ参考にして下さい。
| 築年数 | 要件 |
| 新築〜築42年 | 昭和57年(1982年)1月1日以降に建てられ、新耐震基準を満たすため住宅ローン控除の対象 |
| 築42年〜 | 以下のいずれかの要件を満たすことで住宅ローン控除の対象となる ・「耐震基準適合証明書」を取得している ・「既存住宅性能評価書」による耐震等級評価が等級1~3である ・「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している |
まとめ
本記事では、住宅ローン控除が築年数にどう関係しているのかについて詳しく紹介してきました。
中古住宅が住宅ローン控除の対象になるか調べる際、昭和57(1982)年以前か以降かが重要となってきます。
昭和57(1982)年以前の場合は住宅ローン控除の対象です。
以降の場合は以下の要件を満たすことで控除を受けられます。
- 「耐震基準適合証明書」を取得している
- 「建設住宅性能評価書」による耐震等級評価が等級1~3である
- 「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している
2022年の改正によって中古住宅でも住宅ローン控除を受けやすくなりました。
ぜひ本記事を参考にしながら、住宅ローン控除を最大限活用していきましょう。
ゼロリノベでは住宅ローンに関するセミナーも開催しています。
セミナーでは中古マンションの購入やリノベーションの基礎知識などについても説明していますので、ぜひこちらもご活用下さい。